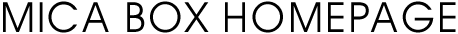
AFRICAN CONCERT 2002 JENAGURU報告
ジンバブエに移住し地元のミュージシャンの自立のためにプロデューサーとして動いている小樽出身の高橋朋子さんから久しぶりに電話があったのは6月頃だっただろうか。毎年のように日本に戻ってきてジンバブエの現状を報告する講演をしたり、ジンバブエのグッズの展示販売などをして資金とネットワークを作ってきた高橋さんとは知り合ってもう5年くらいになり、ジンバブエで作ってもらったシャツを「ぐるぐる」で販売したこともあるが、この数年は会う機会もほとんどなかった。そのシャツはアフリカ人が普段着で着ているデザインの布で作った長袖シャツというもので、現地ではあまりないというもの。夏の短い北海道では長袖の方が便利だからということでオーダーで作ってもらったものだ。すごくいい出来だったが、思ったほどの売れ行きにならず、注文も一回で終わってしまった。僕がモンゴロイドユニットで着ている派手なシャツは、ほとんどこのシリーズのものだ。
最近高橋さんと音信が途絶えていたのは、だいぶ前にジンバブエの音楽を日本で出したいという相談を受けた時に「今の日本では、一部のアフリカファン以外に受け入れられるのは難しいだろう」という反応をしたので、ちょっと引かれてしまったのかもしれない。その頃ビクターでワールドミュージックを担当していたモンゴロイドユニットの鳥居さんを紹介したりしたが、話は進まなかったようである。
彼女の持ってきたジンバブエの音楽はジンバブエでポピュラーなダンスミュージックのスタイルだということだが、刺激が少なくて第一印象が薄いのである。演歌やカントリー&ウェスタンがみんな同じように聞こえるようなもので、地元の人たちには細かい違いがわかるだろうが、外部のものには区別がつかないというような感じだ。
もちろん、バリバリのアフリカ音楽だからポリリズムやシンコペーションはすごいし、ギターのフレーズの絡みなどは、僕にとっても逆立ちしてもかなわないイメージ通りのアフリカがそこにあった。ただ、刺激的な音楽に慣れてしまった耳には、カセットから聞こえてくる音はどこかのどかなものだった。
彼女にとっては「最高」の音楽で、それを日本に紹介したいという思い入れはわかるのだが、「大丈夫、いけますよ」とは言えなかったのだ。
その高橋さんが、この夏にこれまでの活動で築いてきたネットワークを元にジンバブエからミュージシャンを連れてきて「アフリカンコンサート2002 ジャナグル」というツアーをするというのは、「ぐるぐる」に届けられたチラシを見て知った。「北海道アフリカネットワーク」というグループが主体となり、資金的にいろいろ基金などを使ったようで、コンサートだけでなくワークショップのような「公的行事」も混ざるハードなスケジュールで、よくここまでこぎつけたという感じのものだった。
で、突然の電話だったが、用件の一つは使う楽器を探しているということだった。コルグのM1というシンセだが、古い機種ということでもうレンタル機材にはなく、主催関係でも持っている人を見つけられずて困っているらしい。ジンバブエではM1しかなく、いつも使っているのが使いたいのだという。「そんなことならもっと早く聞いてよ、僕持ってるんだから」ということで貸してあげることにした。自分でもまだM1の音は現役で使っているが出番は減っているので一ヶ月くらいならなくても大丈夫だ。
 で、もうひとつ。せっかく日本に着たのだから日本でレコーディングがしてみたい。一日だけオフがあるので安いスタジオを知らないだろうかということだった。札幌にもスタジオはいくつかあり、安いところもあるがプロとしてのクォリティーを持っていて、バンドの録音が出来るというと限られてくる。すぐにいつも使っている「HIT STUDIO」の山本さんに電話をして事情を話し、協力してもらうことになった。といっても、アフリカから来たからといっていちいち安くしていたら営業にならないので、ちゃんと最低限の料金は払ってもらうことにしたが、高橋さんの想定していた範囲だったのでレコーディングは実現することになった。
で、もうひとつ。せっかく日本に着たのだから日本でレコーディングがしてみたい。一日だけオフがあるので安いスタジオを知らないだろうかということだった。札幌にもスタジオはいくつかあり、安いところもあるがプロとしてのクォリティーを持っていて、バンドの録音が出来るというと限られてくる。すぐにいつも使っている「HIT STUDIO」の山本さんに電話をして事情を話し、協力してもらうことになった。といっても、アフリカから来たからといっていちいち安くしていたら営業にならないので、ちゃんと最低限の料金は払ってもらうことにしたが、高橋さんの想定していた範囲だったのでレコーディングは実現することになった。
僕の貸し出すM1にもレンタル料を払うということだったが、まだ会ってはいないものの「ミュージシャン、トモダチ」ということで、その分は録音の費用に回してちょうだい、ということにした。
で、なんだかんだと資料をもらったら来日メンバーにギタリストが一人しかいないことが気になった。ジンバブエの音楽の特徴の一つはギター二本の音の絡みだが、これではさみしい。いろいろお金の関係で二人を連れて来れないのだろう。一人でも問題はないので一人にしたのだろうが二本あったにこしたことはないだろうと思い、おせっかいではあるがジンバブエの高橋さんに「もしギタリストが必要ならお手伝いしようと思うので、リーダーに聞いてみてほしい」とメールしたところ、なんと「必要だと言っている」という返信が来た。日本人にそんな演奏ができるかもわからないのにこの返事なので高橋さんもびっくりしたと思うが、僕はなんとなくこのことに気がついた時にこういう返事が来る確信のようなものがあったし、突然の電話からの流れで彼らとは強い縁を感じていたのだ。
演奏に関しての自信は「たぶん大丈夫だろう」とは思っていた。高校生の時にボサノバを初めて聴いて、そのシンコペーションの虜になって、ギターのバッキングやスネアのリムのリズムを授業中も指で叩いていた。その後ジャズをちょっとかじったり、ニューオリンズの音楽に出会ったり、フェラ・クティ、サニー・アデなどのアフリカンポップスに影響を受けたりと、いつもポリリズムとシンコペーションに惹かれていたような思う。結局ボサノバが好きになってもボサノバギターを修得したわけでもなく、ジャズギターがちゃんと弾けるようになったわけでもない。ロックもブルースにも取り柄がない、なんだかつぶしのきかない、ギタリストと言うのもおこがましいようなギタリストになったわけであるがQUOTATIONSでのギターのフレーズなどはいつもアフリカのような、ラテンのような、そんなシンコペーテッドギターを弾いていたのである。
アフリカンポップスもそんなにたくさん聞いているわけではない。むしろ聞いていないほうかもしれないが、「感覚」は理解していたつもりなので、出来ることならちゃんとやってみたいとは思っていた。でも自分でアフリカ音楽のバンドを作るという気力もなく、その感覚はDTMの中で展開していくことになる。
MICABOXの「ひねもす」も16分音符のシークエンスがベースだが、ノリはバラフォンのような感じのウラのノリで聴き方を間違えると表と裏がわからなくなる。さすがに高遠彩子さんはすぐに歌えたが、過去にこの曲の一拍がつかめず歌えなかったシンガーもいたのだ。
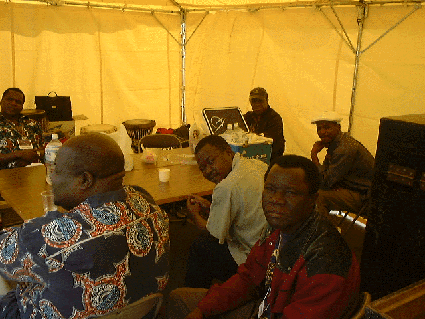 それがジンバブエから「やってみようぜ」という返事が来たのである。ひょんなことから、高校の授業中に始めた練習が実を結ぶことになったのだ。リズムギターはあった方がいいので、やらせてみてダメならキャンセルすればいい、というような感じだったんじゃないだろうか。彼らの言うリズムギターはコードでリズムを刻むのではなく、二小節とか、四小節などのフレーズを延々と繰り返すものである。このフレーズがシンプルなものもあれば、やたらに難しいものがある。今回来日するクライヴ・マルンガのCDを送ってもらって、リズムギターとおぼしきフレーズを聴き取ったのだが、何度聞いてもわからないものもあった。結局一日かかってなんとか譜面にしたが、譜面を見てすぐに弾けるかというと、これまた大変である。ノリが思い出せない。しかも同じフレーズを10分近く弾くというのも経験のないことなので、指がもつかという心配もあった。
それがジンバブエから「やってみようぜ」という返事が来たのである。ひょんなことから、高校の授業中に始めた練習が実を結ぶことになったのだ。リズムギターはあった方がいいので、やらせてみてダメならキャンセルすればいい、というような感じだったんじゃないだろうか。彼らの言うリズムギターはコードでリズムを刻むのではなく、二小節とか、四小節などのフレーズを延々と繰り返すものである。このフレーズがシンプルなものもあれば、やたらに難しいものがある。今回来日するクライヴ・マルンガのCDを送ってもらって、リズムギターとおぼしきフレーズを聴き取ったのだが、何度聞いてもわからないものもあった。結局一日かかってなんとか譜面にしたが、譜面を見てすぐに弾けるかというと、これまた大変である。ノリが思い出せない。しかも同じフレーズを10分近く弾くというのも経験のないことなので、指がもつかという心配もあった。
その後もジンバブエからはいろいろな相談が来た。ひとつはヤマハのFX500というエフェクターをメンバーがいつも使っているのでそれを使いたいのだが、というものだった。僕は知らない機種だったのでネットで検索したら10年くらい前のものだった。小さいものだったので持ってこれるんじゃないかと返事を送ったら「スタジオのものでメンバーは持ち出せない。そんなものですら持っていないんです」ということだった。
話を聞いてみるとジンバブエにも音楽産業があるのだが白人が独占していて、スタジオも一つしかなく、彼らはCDを出しても原盤権も著作権もないらしい。それでクライヴはケンカしてそのスタジオには出入り禁止となっているというような状況で、高橋さんはアフリカ人が自前のスタジオや組織を持つことを目指して活動しているのだそうだ。その名前がショナ族の言葉で「大きな月」を意味する「ジャナグル」で、今、音楽文化センターというものを作ろうとしていて政府から土地を提供してもらうまではこぎつけているらしい。今回、いろいろお金を節約しているのは、いろいろ機材を買って帰りたいのでそのためのお金を残しているのだ。
 こういうことも早く言ってくれれば、使わなくなった古い機材にホコリをかぶせたままにしている人は多いはずなので、新聞で大きく取り上げるとかすれば少しは集まったと思うのに、と思う。電圧の問題は残るけれど。
こういうことも早く言ってくれれば、使わなくなった古い機材にホコリをかぶせたままにしている人は多いはずなので、新聞で大きく取り上げるとかすれば少しは集まったと思うのに、と思う。電圧の問題は残るけれど。
こちらのスタッフが、FX500が売っていたら買ってほしいと言ってきたがどうしよう、と相談してきた。「ちょっと待って。いつも使っているからという理由以外にそれでなくてはならない理由はないと思うので、エフェクターは僕の持っているものを貸すからそれを使ってくれ。それでもどうしてもというのならネットオークションに出ているから買えばいい。」と返事をした。
来日が近くなり、スタッフがM1とエフェクターを取りに来て、最初の地である函館に送ったらすぐ後にボーカル用のエフェクターもないかと連絡が来る。「早く言ってよ」ということで、もうひとつ取りに来てもらった。なんとかツアーは始まったようだが、その後も「ベースアンプのないところがある」とか「借りたアンプが使えるものではなかった」などとトラブルは続いているようだった。どうも主催者の中には音楽の公演をすることを甘く見ているところもあるようだ。手作りも結構だがやることは「興業」でお金も取るのだから最低のレベルはクリアしなければならないがそれを知らない。「いいこと」をしているからって許されるものではないのだが、そのへんがうやむやになることが良くある。こういうケースをこれまで何度も何度も経験して積極的には関わらないようにしているのだが、それでも縁がある時はあるものである。
さて、リズムギターを手伝うとはいってもリハなしでは難しい。ツアーの半ば過ぎ、18日に札幌でコンサートがあるのだが16日に時間がとれるのでその時にライブのリハとレコーディングの準備をしようということになった。16日にメンバーが僕の仕事場に来ることになったのだが、当日彼らを運ぶ足がないということだ。長い間準備をしてきたこのツアーらしいが、車と運転手が全ての時間に用意されていないというのは信じられない。ボランティアスタッフは何十人といると聞いているのだが。
結局僕が迎えに行くことにして、8人乗りなので6人乗ってもらい、残りの3人が地下鉄を乗り継いで近くの駅まで来てもらうことにした。その3人をまた僕がピックアップしに行くわけである。
なんだかなー、と思いながらジンバブエミュージシャンを車に乗せて自宅に戻る。さっそくスタジオに入ってもらい、音を出し始めたら今回一緒にツアーしている日本人のアフリカンドラムグループの「N'DANA」の山北君達三人が到着。前日まではこの3人が来ることは聞いていなかったのでスタジオに入りきるか心配だったが、まずはジンバブエ組と僕とで始めることになった。コーラスの女の子二人と山北君達は別室で待機である。
 何をやるのかなー、と思っていたら、まずジンバブエの親指ピアノ「ムビラ(MBILA)」のアンディーが出す音を皆で聞いている。ムビラは箱形のカリンバと違って本体に共鳴部を持たない。伝統的には瓢箪などの共鳴するものの中などで弾くのだがアンディーのムビラはなんとピックアップ内蔵で、コードをつないでスピーカーから音を出すようになっていた。
何をやるのかなー、と思っていたら、まずジンバブエの親指ピアノ「ムビラ(MBILA)」のアンディーが出す音を皆で聞いている。ムビラは箱形のカリンバと違って本体に共鳴部を持たない。伝統的には瓢箪などの共鳴するものの中などで弾くのだがアンディーのムビラはなんとピックアップ内蔵で、コードをつないでスピーカーから音を出すようになっていた。
なんと伝統曲を元にした新曲のようでこれからバンドの音にしていくらしい。リーダーのクライブがフレーズを考えて歌い、それをそれぞれのパートが演奏してまた聞きながら直すというヘッドアレンジの世界だ。僕も思いついたフレーズを弾いていると「それはこういう風にした方がいい」というような指示が来る。リードギターのフランクとうまく絡み合うように考えていく作業は楽しい。延々とだらだらと一曲が続く。途中で「これをカセットに録音できるか」と言われ急遽録音態勢を作る。普段はこういう時MDで録るのだが彼らはMDなんてものは持っていない。というか知らないかもしれない。ラジカセがなかったのでどうやってカセットに録るのがいいかしばし悩んだが、音が小さかったのでマイクを立ててラインの音と合わせるセッティングにした。
キーボード、ベース、ムビラをラインで音出ししていたが、彼らは大きな音を出さない。とにかく小さく弾く。だからドラムもさわるくらいの叩き方だ。でもリズムはしっかりしていてグルーヴは出ている。
新曲が一段落すると次は僕のパートの確認だ。聞いていたCDの6曲を順番にやっていくが、まず最初の一曲で「グッド・フンガリング」などと言っている。まずは合格といったところだろうか。ところが僕が聞き取っていたパートの多くはリードギターのフランクが弾くもので、練習したフレーズそのままで良かったのは6曲中2曲。あとはその場で新しいフレーズを覚えなければならなくなった。中には指がつりそうになるものもあり、さすがにこりゃ無理か、ということで簡単なフレーズにしてくれたものもあった。僕自身が偏ったギターの弾き方を身につけてしまったせいもあるが、やっぱりアプローチの違いも大きいと実感した。音だけ聞いていると「なんでこんな音の使い方をするんだろう」とものも、実際に弾いているところを見ると合理的だったりする。手癖が全く違うのだ。
 ただ、大事にしているところがリズムだということはよーく理解できた。僕らはどうしても「かっこ良いフレーズ」を求めるが、彼らはまずリズムである。単純なフレーズでもリズムが他のパートとどうオーガニックに結びつくか、ということを重点として考える。だから、一つのパートが変わると他のパートも変えたりする。それを一つずつタペストリーのように編み上げていく感じである。で、曲は2コードか3コードでサビなんてものはない。延々とワンパターンが続く。時折リードギターがフレーズを展開させたりドラムがおかずを入れたりする程度の変化があるだけである。ドラムもバスドラムが一拍ずつのいわゆる「四つ打ち」で両手はほとんどハイハットを叩く。スネアやタムはイントロや歌の出入りでたまに叩くだけ。エンディングに至ってはほとんど「ない」。音を下げていって何となく終わるのだ。けっこう僕好みである。
ただ、大事にしているところがリズムだということはよーく理解できた。僕らはどうしても「かっこ良いフレーズ」を求めるが、彼らはまずリズムである。単純なフレーズでもリズムが他のパートとどうオーガニックに結びつくか、ということを重点として考える。だから、一つのパートが変わると他のパートも変えたりする。それを一つずつタペストリーのように編み上げていく感じである。で、曲は2コードか3コードでサビなんてものはない。延々とワンパターンが続く。時折リードギターがフレーズを展開させたりドラムがおかずを入れたりする程度の変化があるだけである。ドラムもバスドラムが一拍ずつのいわゆる「四つ打ち」で両手はほとんどハイハットを叩く。スネアやタムはイントロや歌の出入りでたまに叩くだけ。エンディングに至ってはほとんど「ない」。音を下げていって何となく終わるのだ。けっこう僕好みである。
5分も延々と同じフレーズを演奏していると、ちょっと変えたくなるのが我々である。変えないつもりでも「魔が差した」ように勝手に指が別のことを弾いてしまったりする。そしてやってることがわからなくなったりする。でも彼らは平気な顔で正確に同じことを繰り返し、観客はそれでトランスになるのだろう。これがジンバブエのダンス音楽のZIT MUSICということらしい。メンバーはおそらくレゲエをやれと言われればやれるだろうし、ロックっぽくも出来るのだろうが、ストイックなまでにZIT MUSICに徹しているのがクライブ・マルンガのバンドのようだ。ミュージシャンと観客が、ステージの上で「俺たちが盛り上げるからおまえら踊れ」とか客席から「金払っているんだからその分楽しませろ」という関係でなく、「我々の音楽」というのがひとつあって、どちらもそれを成り立たせる大事な役目をし合っているということだろう。これはモンゴロイドユニットがやろうとしていることと同じである。
やってみて実感したことは「気持ちがいい」と言うことだ。演奏している自分は一つのパートを機械のように弾いているが、体に返ってくるのは一人一人の演奏が絡み合って出来上がった生き物である。延々とリズムが続くのはクラブミュージックの要素と似ているが、音量は小さいし、ここには刺激的な要素はない。ジンバブエにだって他の音楽が流入しているだろうに、これだけでハイになれるとは幸せなことである。
6曲中4曲のフレーズが差し替えられて頭はほとんどパニック状態だったが、なんとかこの日のリハを終わらせた。メンバーからは「おまえ、覚えるの早いやんけ」みたいに言われたが「消えるのも早いんだから」と必死にMD録音した。でもあらかじめ練習していた2曲は「パーフェクト」と言われ一安心。後は指がもつかである。早くもリハ中に指がつってしまったし。
18日は札幌芸術の森という美術館や工芸アトリエなどが並ぶ公共施設の中の野外ステージなのだが、サウンドチェックがなんと朝8時。前の日にもコンサートがあり、音響機材をそのまま使うので開館前にすませたいということらしい。7時半の地下鉄に乗り、15分ほど遅れて到着。すぐにサウンドチェックが始まったが、彼らの出す生音の小さいこと。ギターアンプから出る音は聞こえるか聞こえないかのギリギリで、モニターからはドラムだけ返して、なんて言っている。よほど耳がいいのかな。砂漠には小さな星まで見える人たちがいるらしいがそんな感じで耳がいいのかもしれない。僕は自分の音がちゃんと聞けないと演奏できないタイプだから、アンプので音を大きくしたが、隣のフランクの音もちゃんと聞きたいので上げすぎるわけにも行かずちょっとだけにした。
 その後控え室でギターだけアンプにつないで最後のリハ。主にイントロの入り方の練習などをやった。ドラムがないのでドラマーが口で「シューッ」などと言って口ドラムする。あれはオープンハイハットのことみたいだ。そんな小さな音でベースもなしに練習が出来てしまうのも嬉しい。細野組ではたまにホテルの部屋で身近なもので音を出すことはあるが、いつの間にか全て揃わないと練習できないという勘違いの世界に入ってしまっているかもしれない、日本人は。いつも寝てばっかりいるコーラスの子達も歌い出すとすごくいい。おそらく決まりきったパターンというのがあるんだろうがヘッドアレンジで曲がどんどん固まっていく。
その後控え室でギターだけアンプにつないで最後のリハ。主にイントロの入り方の練習などをやった。ドラムがないのでドラマーが口で「シューッ」などと言って口ドラムする。あれはオープンハイハットのことみたいだ。そんな小さな音でベースもなしに練習が出来てしまうのも嬉しい。細野組ではたまにホテルの部屋で身近なもので音を出すことはあるが、いつの間にか全て揃わないと練習できないという勘違いの世界に入ってしまっているかもしれない、日本人は。いつも寝てばっかりいるコーラスの子達も歌い出すとすごくいい。おそらく決まりきったパターンというのがあるんだろうがヘッドアレンジで曲がどんどん固まっていく。
コンサートは午後1時スタート。札幌のアフリカンダンスグループが大勢で雰囲気を作り、「N'DANA」がそれをまた盛り上げた。やはり一般の人たちにはアフリカといえば太鼓だし、その点では「N'DANA」は日本人のイメージ通りの音を出すので受けていた。しかし、日本人はあらゆるジャンルの音楽で本場並みのことが出来てしまうのだなあと改めて不思議に思った。
そしていよいよクライブのバンドである。最初の一曲でムビラの新曲をやる。僕はまずこの一曲を弾いてすぐ引っ込むので、なんのインフォメーションもないお客さんには「ありゃなんだ??」という感じだったことだろう。後半改めて紹介されてステージへ出る。おとなしいサウンドなのでお客さんのノリが心配だったが、野外でビールを飲んだりしているせいか、いい感じで盛り上がっていた。なんと言っても見た目にはコーラスの女の子二人のダンスがすごいから、これが効いている感じである。これも日本人の期待するアフリカのイメージに応えてくれる。
 僕も本番のステージは気持ちよく演奏できた。突然メンバーが踊り出したらどうしようかと心配もしたが、フロントの三人以外は皆おとなしいもので、淡々と演奏を進める。が、ポーカーフェイスでやっているように見えて、けっこう楽しんでいるのだ。まったく僕好み。目の前で自分が加わっている演奏で「ホンモノ」のアフリカンダンスが繰り広げられているのには感動した。しかし、彼女たちのお尻の大きいことといったら...。
さて、心配していた長さであるが、これはリハより短かった。ちょっと拍子抜けしたが、それがわかれば最初から飛ばすというものである。楽しませてもらった。後日細野さんにこのことを報告したら「現地の人たちと一緒に演奏するということはめったに出来ることではないので羨ましい限りだ」という返事が来た。まったく縁というものは面白いものだ。細野さんはかつて、サニー・アデだったか、一緒にやりそうな話になったのだが、縁がなく流れたらしい。
僕も本番のステージは気持ちよく演奏できた。突然メンバーが踊り出したらどうしようかと心配もしたが、フロントの三人以外は皆おとなしいもので、淡々と演奏を進める。が、ポーカーフェイスでやっているように見えて、けっこう楽しんでいるのだ。まったく僕好み。目の前で自分が加わっている演奏で「ホンモノ」のアフリカンダンスが繰り広げられているのには感動した。しかし、彼女たちのお尻の大きいことといったら...。
さて、心配していた長さであるが、これはリハより短かった。ちょっと拍子抜けしたが、それがわかれば最初から飛ばすというものである。楽しませてもらった。後日細野さんにこのことを報告したら「現地の人たちと一緒に演奏するということはめったに出来ることではないので羨ましい限りだ」という返事が来た。まったく縁というものは面白いものだ。細野さんはかつて、サニー・アデだったか、一緒にやりそうな話になったのだが、縁がなく流れたらしい。
彼らとは21日に浦河でもう一度一緒に演奏し、19日、26日には札幌でレコーディングを手伝った。レコーディングは時間がなかったので演奏には参加せず、ほとんどディレクターだったが正味二日で8曲を録音し、マスタリングまで済ませたのは驚異のスピードである。
レコーディングについてはまたエピソード満載であるが、長くなったのでここでひとまず報告はおしまい。CDになった時にでも書いてみたい。
掲載したコンサートの写真は植村佳弘氏より提供していただいた。(三上敏視)
CONTACT
MICABOX
BACK TO OLD HOME
BACK TO NEW TOP
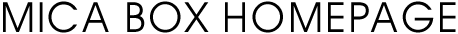
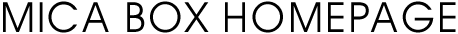
 で、もうひとつ。せっかく日本に着たのだから日本でレコーディングがしてみたい。一日だけオフがあるので安いスタジオを知らないだろうかということだった。札幌にもスタジオはいくつかあり、安いところもあるがプロとしてのクォリティーを持っていて、バンドの録音が出来るというと限られてくる。すぐにいつも使っている「HIT STUDIO」の山本さんに電話をして事情を話し、協力してもらうことになった。といっても、アフリカから来たからといっていちいち安くしていたら営業にならないので、ちゃんと最低限の料金は払ってもらうことにしたが、高橋さんの想定していた範囲だったのでレコーディングは実現することになった。
で、もうひとつ。せっかく日本に着たのだから日本でレコーディングがしてみたい。一日だけオフがあるので安いスタジオを知らないだろうかということだった。札幌にもスタジオはいくつかあり、安いところもあるがプロとしてのクォリティーを持っていて、バンドの録音が出来るというと限られてくる。すぐにいつも使っている「HIT STUDIO」の山本さんに電話をして事情を話し、協力してもらうことになった。といっても、アフリカから来たからといっていちいち安くしていたら営業にならないので、ちゃんと最低限の料金は払ってもらうことにしたが、高橋さんの想定していた範囲だったのでレコーディングは実現することになった。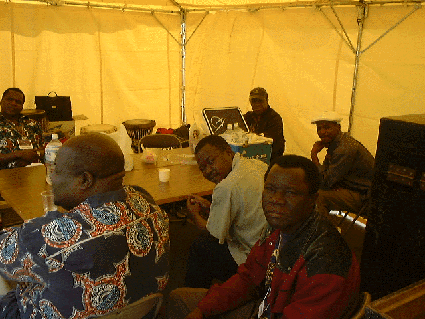 それがジンバブエから「やってみようぜ」という返事が来たのである。ひょんなことから、高校の授業中に始めた練習が実を結ぶことになったのだ。リズムギターはあった方がいいので、やらせてみてダメならキャンセルすればいい、というような感じだったんじゃないだろうか。彼らの言うリズムギターはコードでリズムを刻むのではなく、二小節とか、四小節などのフレーズを延々と繰り返すものである。このフレーズがシンプルなものもあれば、やたらに難しいものがある。今回来日するクライヴ・マルンガのCDを送ってもらって、リズムギターとおぼしきフレーズを聴き取ったのだが、何度聞いてもわからないものもあった。結局一日かかってなんとか譜面にしたが、譜面を見てすぐに弾けるかというと、これまた大変である。ノリが思い出せない。しかも同じフレーズを10分近く弾くというのも経験のないことなので、指がもつかという心配もあった。
それがジンバブエから「やってみようぜ」という返事が来たのである。ひょんなことから、高校の授業中に始めた練習が実を結ぶことになったのだ。リズムギターはあった方がいいので、やらせてみてダメならキャンセルすればいい、というような感じだったんじゃないだろうか。彼らの言うリズムギターはコードでリズムを刻むのではなく、二小節とか、四小節などのフレーズを延々と繰り返すものである。このフレーズがシンプルなものもあれば、やたらに難しいものがある。今回来日するクライヴ・マルンガのCDを送ってもらって、リズムギターとおぼしきフレーズを聴き取ったのだが、何度聞いてもわからないものもあった。結局一日かかってなんとか譜面にしたが、譜面を見てすぐに弾けるかというと、これまた大変である。ノリが思い出せない。しかも同じフレーズを10分近く弾くというのも経験のないことなので、指がもつかという心配もあった。 こういうことも早く言ってくれれば、使わなくなった古い機材にホコリをかぶせたままにしている人は多いはずなので、新聞で大きく取り上げるとかすれば少しは集まったと思うのに、と思う。電圧の問題は残るけれど。
こういうことも早く言ってくれれば、使わなくなった古い機材にホコリをかぶせたままにしている人は多いはずなので、新聞で大きく取り上げるとかすれば少しは集まったと思うのに、と思う。電圧の問題は残るけれど。 何をやるのかなー、と思っていたら、まずジンバブエの親指ピアノ「ムビラ(MBILA)」のアンディーが出す音を皆で聞いている。ムビラは箱形のカリンバと違って本体に共鳴部を持たない。伝統的には瓢箪などの共鳴するものの中などで弾くのだがアンディーのムビラはなんとピックアップ内蔵で、コードをつないでスピーカーから音を出すようになっていた。
何をやるのかなー、と思っていたら、まずジンバブエの親指ピアノ「ムビラ(MBILA)」のアンディーが出す音を皆で聞いている。ムビラは箱形のカリンバと違って本体に共鳴部を持たない。伝統的には瓢箪などの共鳴するものの中などで弾くのだがアンディーのムビラはなんとピックアップ内蔵で、コードをつないでスピーカーから音を出すようになっていた。 ただ、大事にしているところがリズムだということはよーく理解できた。僕らはどうしても「かっこ良いフレーズ」を求めるが、彼らはまずリズムである。単純なフレーズでもリズムが他のパートとどうオーガニックに結びつくか、ということを重点として考える。だから、一つのパートが変わると他のパートも変えたりする。それを一つずつタペストリーのように編み上げていく感じである。で、曲は2コードか3コードでサビなんてものはない。延々とワンパターンが続く。時折リードギターがフレーズを展開させたりドラムがおかずを入れたりする程度の変化があるだけである。ドラムもバスドラムが一拍ずつのいわゆる「四つ打ち」で両手はほとんどハイハットを叩く。スネアやタムはイントロや歌の出入りでたまに叩くだけ。エンディングに至ってはほとんど「ない」。音を下げていって何となく終わるのだ。けっこう僕好みである。
ただ、大事にしているところがリズムだということはよーく理解できた。僕らはどうしても「かっこ良いフレーズ」を求めるが、彼らはまずリズムである。単純なフレーズでもリズムが他のパートとどうオーガニックに結びつくか、ということを重点として考える。だから、一つのパートが変わると他のパートも変えたりする。それを一つずつタペストリーのように編み上げていく感じである。で、曲は2コードか3コードでサビなんてものはない。延々とワンパターンが続く。時折リードギターがフレーズを展開させたりドラムがおかずを入れたりする程度の変化があるだけである。ドラムもバスドラムが一拍ずつのいわゆる「四つ打ち」で両手はほとんどハイハットを叩く。スネアやタムはイントロや歌の出入りでたまに叩くだけ。エンディングに至ってはほとんど「ない」。音を下げていって何となく終わるのだ。けっこう僕好みである。 その後控え室でギターだけアンプにつないで最後のリハ。主にイントロの入り方の練習などをやった。ドラムがないのでドラマーが口で「シューッ」などと言って口ドラムする。あれはオープンハイハットのことみたいだ。そんな小さな音でベースもなしに練習が出来てしまうのも嬉しい。細野組ではたまにホテルの部屋で身近なもので音を出すことはあるが、いつの間にか全て揃わないと練習できないという勘違いの世界に入ってしまっているかもしれない、日本人は。いつも寝てばっかりいるコーラスの子達も歌い出すとすごくいい。おそらく決まりきったパターンというのがあるんだろうがヘッドアレンジで曲がどんどん固まっていく。
その後控え室でギターだけアンプにつないで最後のリハ。主にイントロの入り方の練習などをやった。ドラムがないのでドラマーが口で「シューッ」などと言って口ドラムする。あれはオープンハイハットのことみたいだ。そんな小さな音でベースもなしに練習が出来てしまうのも嬉しい。細野組ではたまにホテルの部屋で身近なもので音を出すことはあるが、いつの間にか全て揃わないと練習できないという勘違いの世界に入ってしまっているかもしれない、日本人は。いつも寝てばっかりいるコーラスの子達も歌い出すとすごくいい。おそらく決まりきったパターンというのがあるんだろうがヘッドアレンジで曲がどんどん固まっていく。 僕も本番のステージは気持ちよく演奏できた。突然メンバーが踊り出したらどうしようかと心配もしたが、フロントの三人以外は皆おとなしいもので、淡々と演奏を進める。が、ポーカーフェイスでやっているように見えて、けっこう楽しんでいるのだ。まったく僕好み。目の前で自分が加わっている演奏で「ホンモノ」のアフリカンダンスが繰り広げられているのには感動した。しかし、彼女たちのお尻の大きいことといったら...。
さて、心配していた長さであるが、これはリハより短かった。ちょっと拍子抜けしたが、それがわかれば最初から飛ばすというものである。楽しませてもらった。後日細野さんにこのことを報告したら「現地の人たちと一緒に演奏するということはめったに出来ることではないので羨ましい限りだ」という返事が来た。まったく縁というものは面白いものだ。細野さんはかつて、サニー・アデだったか、一緒にやりそうな話になったのだが、縁がなく流れたらしい。
僕も本番のステージは気持ちよく演奏できた。突然メンバーが踊り出したらどうしようかと心配もしたが、フロントの三人以外は皆おとなしいもので、淡々と演奏を進める。が、ポーカーフェイスでやっているように見えて、けっこう楽しんでいるのだ。まったく僕好み。目の前で自分が加わっている演奏で「ホンモノ」のアフリカンダンスが繰り広げられているのには感動した。しかし、彼女たちのお尻の大きいことといったら...。
さて、心配していた長さであるが、これはリハより短かった。ちょっと拍子抜けしたが、それがわかれば最初から飛ばすというものである。楽しませてもらった。後日細野さんにこのことを報告したら「現地の人たちと一緒に演奏するということはめったに出来ることではないので羨ましい限りだ」という返事が来た。まったく縁というものは面白いものだ。細野さんはかつて、サニー・アデだったか、一緒にやりそうな話になったのだが、縁がなく流れたらしい。